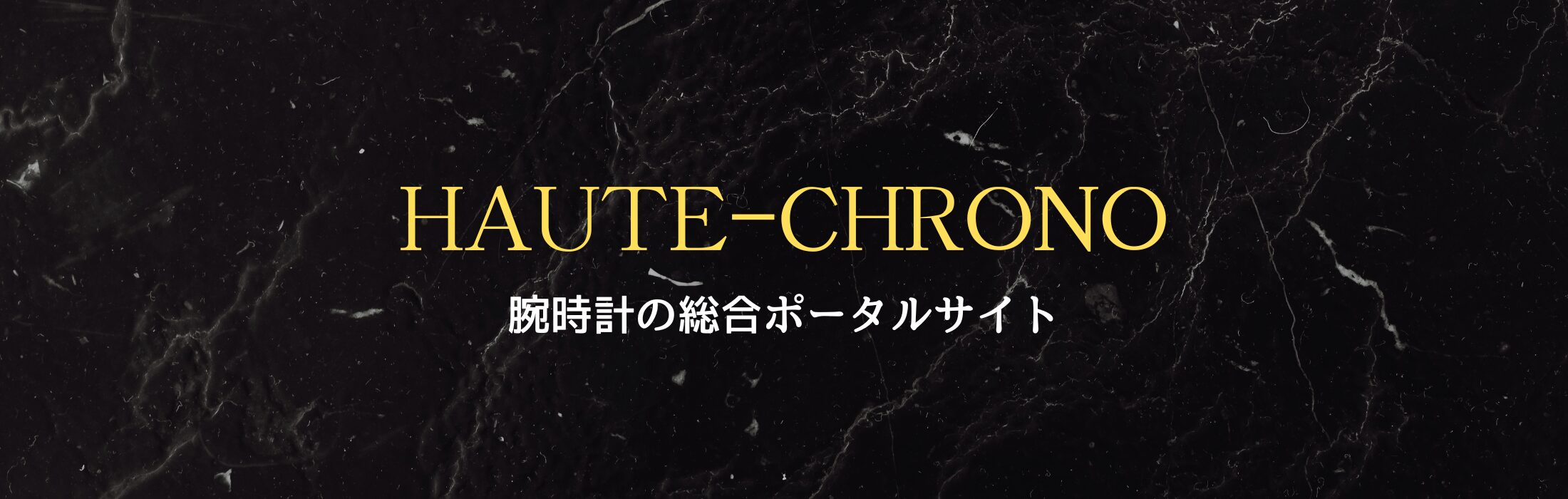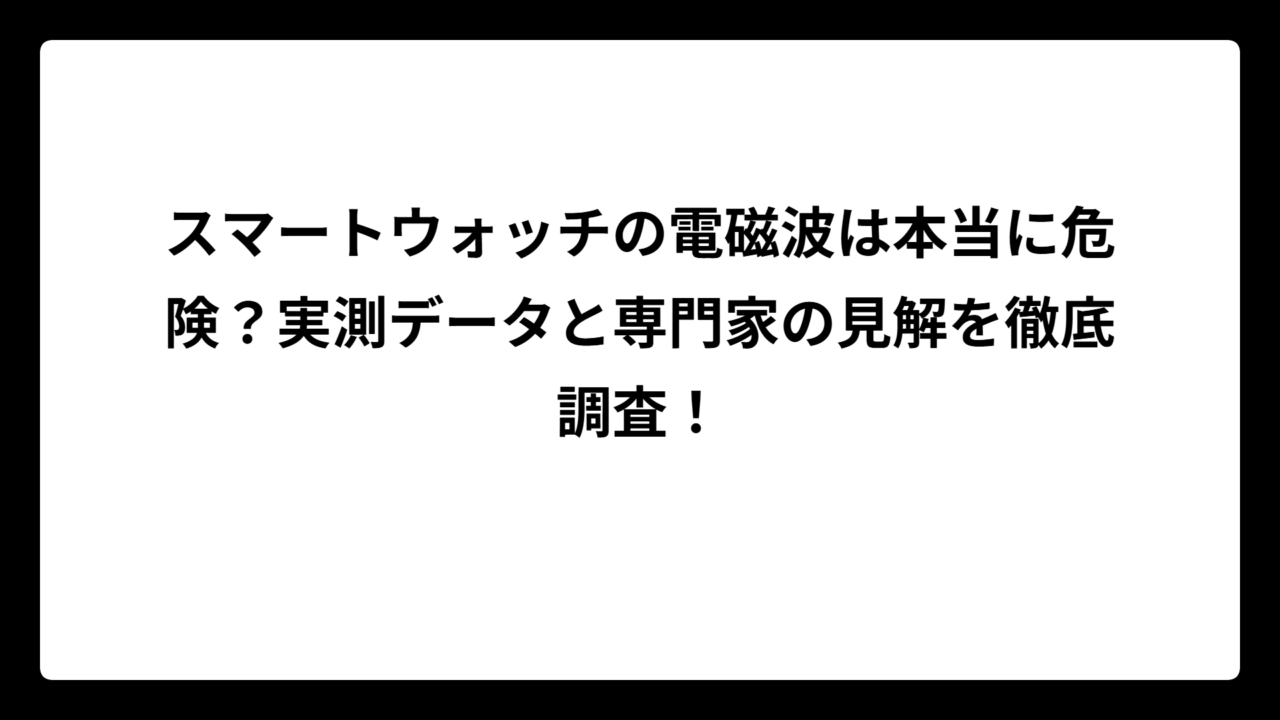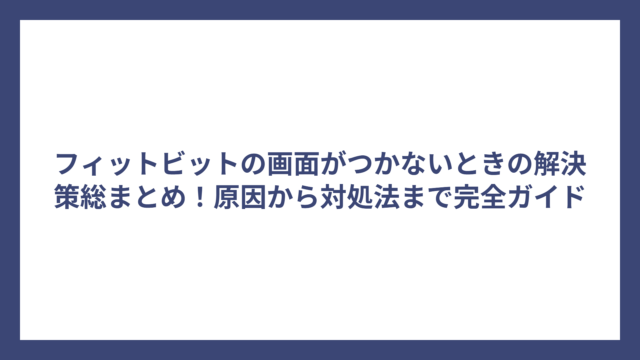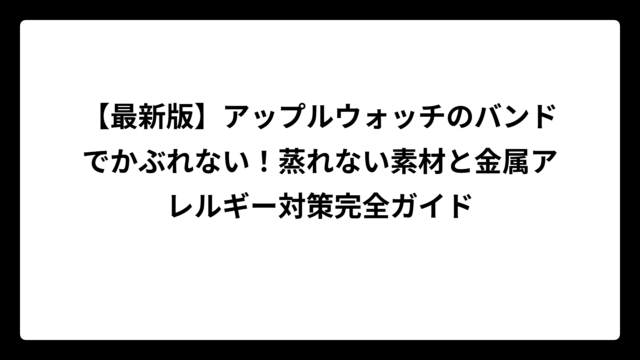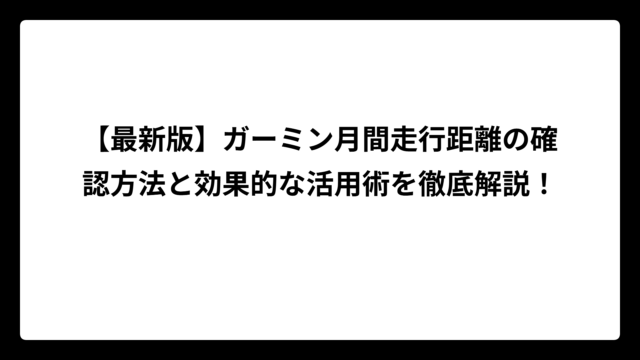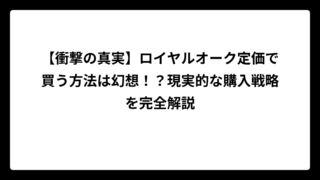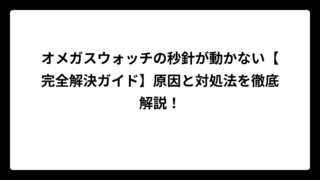スマートウォッチを毎日身に着けている方なら、一度は「電磁波の影響は大丈夫なのか?」と疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。特に24時間装着することが多いスマートウォッチの場合、その電磁波が体に与える影響について心配になるのは当然です。
この記事では、ネット上に散らばるスマートウォッチの電磁波に関する情報を徹底的に調べ上げ、実際の測定データや臨床事例、専門家の見解をわかりやすくまとめました。単なる憶測ではなく、科学的根拠に基づいた情報をお届けします。実際にスマートウォッチを着用した時に膝の痛みが出現した臨床事例から、電磁波測定器による具体的な数値データ、WHOや専門家の公式見解まで、あなたが知りたい情報が網羅されています。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ スマートウォッチから発生する電磁波の実測データと安全基準値の比較 |
| ✅ 実際に症状が現れた臨床事例とその対処法 |
| ✅ 妊娠中や赤ちゃんへの影響に関する専門機関の見解 |
| ✅ 電磁波の影響を軽減する具体的な対策方法 |
スマートウォッチの電磁波測定と健康への実際の影響
- スマートウォッチの電磁波測定で判明した具体的な数値データ
- 実際にスマートウォッチの電磁波で症状が現れた臨床事例の詳細
- 電磁波の種類と周波数による人体への影響の違い
- WHOや専門機関が示すスマートウォッチ電磁波の安全性
- 電磁波過敏症の実態と症状の特徴
- 裏蓋の材質による電磁波シールド効果の検証結果
スマートウォッチの電磁波測定で判明した具体的な数値データ
スマートウォッチから実際にどの程度の電磁波が発生しているのか、専門的な測定器を使った調査結果が明らかになっています。測定には高周波専用のTM-195という測定器が使用され、2.4GHz帯のBluetooth通信の電磁波が測定されました。
📊 スマートウォッチの電磁波測定結果
| 状態 | 測定値(μW/cm²) | 測定条件 |
|---|---|---|
| 何もない状態 | 0.139 | 環境の基準値 |
| スリープ時 | 2.534 | 通常の装着状態 |
| データダウンロード時 | 6.923 | アプリ更新中 |
| スマートフォン(参考) | 16.784 | スリープ時の最大値 |
この測定結果を見ると、スマートウォッチのスリープ時の電磁波は2.534μW/cm²となっており、これは世界で最も厳しいとされるスイス・イタリアの規制値9.5μW/cm²を大きく下回っています。
興味深いのは、スマートバンドを用いた別の測定でもほぼ同様の2.304μW/cm²という数値が記録されていることです。これは、デバイスの形状や材質に関わらず、Bluetooth通信による電磁波の発生量が比較的一定であることを示しています。
ただし、アプリの更新やデータのダウンロード時には6.923μW/cm²まで上昇することも確認されており、このような状況では腕から外すことが推奨される場合もあります。測定は30秒間の最大値を記録するMAXモードで行われているため、実際には瞬間的な最大値であり、常にこの数値の電磁波を浴び続けているわけではありません。
実際にスマートウォッチの電磁波で症状が現れた臨床事例の詳細
整体院での実際の臨床事例として、69歳女性がスマートウォッチを装着することで膝の痛みが悪化する現象が報告されています。この事例は、電磁波の人体への影響を非常に分かりやすく示したケースとして注目されています。
⚡ 臨床事例の詳細な経過
この患者さんは20年間続く膝の痛みで正座ができない状態でした。施術後、スマートウォッチを外した状態では「20年ぶりに正座できました!」と驚かれるほど改善しました。しかし、スマートウォッチを再び装着すると「え?痛い、、、」と膝の痛みが再発することが確認されました。
さらに興味深いことに、この患者さんは11年前から**「左目がよくピクピクする(眼輪筋の痙攣)」「顔の左側だけ赤らむ&汗をよくかく」**といった症状も併発していました。スマートウォッチの使用を中止した結果、2回目の来院時には「目のピクピクは減ってきました」、3回目には「目のピクピクは全然なくなりました!」という改善が見られました。
この事例から分かることは、電磁波の影響は個人差が大きいということです。多くの人には影響がなくても、体質や健康状態によっては明らかな症状として現れる場合があります。
💡 症状改善のポイント
- スマートウォッチの使用を中止
- スマートフォンも就寝時は体から離す
- 加工肉など添加物の多い食品を控える
- 肝機能を改善する水素療法の併用
このケースでは、電磁波対策だけでなく、食生活の改善も併せて行うことで、より効果的な症状改善が得られています。
電磁波の種類と周波数による人体への影響の違い
スマートウォッチから発生する電磁波を理解するためには、電磁波の種類と周波数による影響の違いを知ることが重要です。私たちの身の回りには様々な周波数の電磁波が存在しており、それぞれ異なる特性を持っています。
📡 電磁波の分類と発生源
| 分類 | 周波数 | 主な発生源 | 人体への影響 |
|---|---|---|---|
| 低周波 | 300Hz以下 | 家電製品、送電線 | 神経刺激作用 |
| 中間周波 | 300Hz〜10MHz | IH調理器、ICカード | 熱作用が主 |
| 高周波 | 10MHz以上 | スマホ、Wi-Fi、電子レンジ | 熱作用 |
スマートウォッチは2.4GHz帯のBluetooth通信を使用しているため、高周波の電磁波に分類されます。この周波数帯は、電子レンジと同じ周波数帯ですが、出力が大幅に異なるため人体への影響も大きく違います。
電子レンジは1kW(1000W)という大出力で食品を加熱しますが、スマートウォッチのBluetooth通信は**わずか10mW未満、実際には10μWで稼働することも多く「チリみたいな熱量」**と専門家は表現しています。
⚠️ 電磁波の人体作用メカニズム
- 刺激作用:低周波でビリビリとした感覚
- 熱作用:高周波で体温が上昇する現象
- 非熱作用:科学的に立証されていない影響
重要なのは、電磁波の影響は強度×時間で決まることです。スマートウォッチのように低出力の電磁波を長時間浴びることと、高出力の電磁波を短時間浴びることでは、人体への影響が異なる可能性があります。
WHOや専門機関が示すスマートウォッチ電磁波の安全性
世界保健機関(WHO)をはじめとする国際的な専門機関は、スマートウォッチレベルの電磁波について明確な安全性の見解を示しています。これらの公式見解は、30年以上にわたる膨大な研究データに基づいています。
🏛️ WHO等の公式見解
WHOは1996年から電磁波の健康への影響について検証を続けており、現在のところスマートウォッチから発する程度の電磁波が健康に悪影響を与える証拠はないと結論づけています。スマートウォッチから放たれる電磁波は、X線と違い非電離放射線であるため、人体に悪影響を与えるとは考えられていません。
興味深いことに、電磁波の発がん性リスクはコーヒーや漬物と同程度とされており、日常生活で特別に警戒する必要はないレベルと評価されています。
📊 各国の電磁波規制値比較
| 国・地域 | 規制値(μW/cm²) | 備考 |
|---|---|---|
| スイス・イタリア | 9.5 | 最も厳しい規制 |
| 日本 | 1000 | スイスの約100倍 |
| スマートウォッチ実測値 | 2.5〜7 | 最も厳しい規制の範囲内 |
この表からも分かるように、スマートウォッチの実測値は世界で最も厳しい規制値も下回っているのが現状です。
💭 専門家のコメント要約
- 物理学の観点:周波数の高い紫外線でも皮膚がんの要因程度、それより低い電磁波の害は理論的に説明困難
- 医学の観点:理論値より動物実験、動物実験より人間での臨床試験を重視する立場
- 工学の観点:Bluetooth Low Energyの出力は携帯電話の1/25程度で「気にするな」レベル
電磁波過敏症の実態と症状の特徴
電磁波過敏症(EHS:Electromagnetic Hypersensitivity)は、非常に低いレベルの電磁波でも頭痛・めまい・吐き気・皮膚のヒリヒリ感などの症状を訴える状態です。実際の体験談では、Apple Watchを装着すると「頭のこめかみあたりが締めつけられ、歯もちょっとイリイリした」という症状が報告されています。
⚡ 電磁波過敏症の主な症状
| 症状カテゴリ | 具体的な症状 | 発症タイミング |
|---|---|---|
| 神経系 | 頭痛、めまい、集中力低下 | 電磁波機器の近く |
| 皮膚系 | ヒリヒリ感、発疹、かゆみ | 直接接触時 |
| 消化器系 | 吐き気、胃の不快感 | 長時間曝露後 |
| 循環器系 | 動悸、血圧変動 | ストレス反応として |
しかし、WHOの見解では**「電磁波が原因ではないと考えられている」**とされています。症状の発生が電磁波を浴びたことと関連する科学的根拠がないことから、実際の原因として以下の要因が挙げられています。
🔍 電磁波過敏症の真の原因(WHO見解)
- 生活環境:騒音、光、化学物質など複合的な環境要因
- ストレス:現代社会の様々なストレス要因
- 恐怖心理:電磁波の健康影響を恐れる気持ちそのもの
興味深いことに、化学物質過敏症患者の半数が電磁波過敏症を発症すると言われており、これは共通の体質的要因や心理的要因が関与している可能性を示唆しています。
実際の体験談でも、「散歩に行くときにつけて歩いてみました。すると、いつもと同じルートなのに、体がしんどい」という症状が現れ、Apple Watchを外すと「いつもの通り、普通に歩ける」ようになったと報告されています。
裏蓋の材質による電磁波シールド効果の検証結果
スマートウォッチの裏蓋の材質が電磁波の人体への影響を軽減する可能性について、実際の測定による検証が行われています。特に注目されるのは、金属製裏蓋のシールド効果です。
🔧 裏蓋材質による電磁波対策の検証
CASIO プロトレック WSD-F30の場合、裏蓋には鍛造ステンレスが使用されており、導通テストでは電気が通ることが確認されています。理論的には、この金属製裏蓋がマイクロ波のシールド効果を持つはずです。
しかし、実際の測定結果は興味深いものでした:
| デバイス | 裏蓋材質 | 測定値(μW/cm²) | シールド効果 |
|---|---|---|---|
| CASIO プロトレック | 鍛造ステンレス | 2.534 | 期待されたが… |
| Xiaomi スマートバンド | 樹脂 | 2.304 | ほぼ同じ値 |
| Apple Watch | センサー部以外樹脂 | 推定値 | データなし |
樹脂製裏蓋のスマートバンドでも、金属製裏蓋のスマートウォッチとほぼ同じ数値が記録されたため、裏蓋の金属はあまり関係ない可能性が示唆されています。
これは、電磁波の発生源が裏蓋ではなく、内部のBluetoothモジュールや心拍センサーであり、これらからの電磁波は様々な方向に放射されるためと考えられます。
💡 スマートウォッチの電磁波発生部位
- Bluetoothアンテナ:スマートフォンとの通信用
- 光学式心拍センサー:緑色LED光による測定
- 血中酸素センサー:赤色LED光による測定
- GPS・Wi-Fiアンテナ:位置情報取得用
したがって、裏蓋の材質よりも、これらの機能をオフにすることの方が電磁波低減には効果的と考えられます。
スマートウォッチ電磁波の対策と安全な使用方法
- 妊娠中・赤ちゃんへのスマートウォッチ電磁波の影響と対策
- 電磁波の影響を軽減する具体的な使用方法
- スマートウォッチの機能設定による電磁波削減テクニック
- 電磁波測定器による自宅での電磁波チェック方法
- 健康管理とのバランスを考えた賢いスマートウォッチ活用法
- 体に異変を感じた時の対処法と相談先
- まとめ:スマートウォッチ電磁波との上手な付き合い方
妊娠中・赤ちゃんへのスマートウォッチ電磁波の影響と対策
妊娠中のお母さんにとって、スマートウォッチの電磁波が赤ちゃんに与える影響は最も気になる点の一つです。電磁界情報センターの調査によると、約半数のお母さんがスマートフォンや電子機器に不安を感じているという結果が出ています。
🤱 妊娠中のお母さんの電磁波に対する不安調査結果
| 心配な健康影響 | 割合 | 具体的な不安内容 |
|---|---|---|
| 赤ちゃんの発育 | 最多 | 成長への悪影響 |
| 奇形リスク | 上位 | 先天性異常の心配 |
| 流産・早産 | 上位 | 妊娠継続への影響 |
| 小児白血病 | 一定数 | 将来の病気リスク |
しかし、専門機関の見解は明確です。家電製品やスマートフォンからの電磁波はからだに蓄積されず、遺伝子を傷つける作用もないため、電磁波を浴びている時間や回数には関係なく健康への影響はないとされています。
⚕️ 妊娠中のスマートウォッチ使用に関する専門見解
普段の生活環境で浴びる電磁波の強さは、国際的なガイドライン値を大きく下回っています。スマートウォッチから発生する高周波の電磁波についても同様に低いレベルと考えられています。
重要なのは、電磁波の健康影響を考える時に重要なのは電磁波の強さであり、スマートウォッチからの電磁波は十分な安全率を見込んだ国際的なガイドライン値よりも更に低く、健康に影響があるとは考えられていません。
それでも心配な妊娠中のお母さんには、以下の対策が推奨されています:
🛡️ 妊娠中の電磁波対策(安心のための工夫)
- 就寝時は外す:睡眠中はスマートウォッチを外して充電
- 距離を保つ:電磁波は距離に応じて急激に弱くなる性質を活用
- 機能の選択使用:心拍測定など必要な機能のみ有効化
- ハンズフリー活用:スマートフォンとの組み合わせでより安全に
電磁波の影響を軽減する具体的な使用方法
スマートウォッチの電磁波影響を最小限に抑えるための具体的な使用テクニックをまとめました。これらの方法は、科学的根拠に基づいた対策から、心理的安心感を得るための工夫まで幅広くカバーしています。
⏰ 時間的な使用制限による対策
| 使用パターン | リスクレベル | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 24時間装着 | 理論上最高 | 就寝時は外す |
| 日中のみ装着 | 中程度 | 自宅では外す時間を作る |
| 運動時のみ装着 | 最低 | 必要な時だけの使用 |
実際の臨床事例でも、スマートウォッチの使用を中止した患者さんで症状の改善が見られています。特に就寝時の使用を控えることで、体の自然な回復力を妨げない環境を作ることができます。
📍 距離による電磁波軽減効果
電磁波は発生源から距離が離れると急激に弱くなる性質があります。この特性を活用した対策方法:
- 就寝時:ベッドサイドの充電台に置く(体から50cm以上離す)
- 作業時:デスクワーク中は時々外して机の上に置く
- 入浴時:完全に体から離す時間を作る
- 運動後:汗を拭く際に一時的に外すタイミングを活用
🔄 ローテーション装着による負荷分散
一箇所に集中的に電磁波を浴びることを避けるための工夫:
| 装着位置 | 時間配分 | メリット |
|---|---|---|
| 左手首 | 午前中 | 心拍測定の精度確保 |
| 右手首 | 午後 | 皮膚への圧迫分散 |
| ポケット | 移動時 | 歩数計測は維持 |
| バッグ内 | 不要時 | 完全な電磁波回避 |
スマートウォッチの機能設定による電磁波削減テクニック
スマートウォッチから発生する電磁波を設定変更によって削減する方法があります。全ての機能を停止する必要はなく、必要な機能だけを選択的に使用することで電磁波を最小限に抑えることが可能です。
⚙️ 電磁波削減のための機能設定
| 機能 | 電磁波発生 | 削減方法 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 心拍測定 | 光学センサー | 測定間隔を延長 | 緑色LED光の削減 |
| 血中酸素測定 | 光学センサー | 手動測定に変更 | 赤色LED光の削減 |
| Bluetooth通信 | 高周波 | 同期間隔を延長 | 通信頻度の削減 |
| GPS機能 | 高周波 | 必要時のみON | 位置情報通信の削減 |
緑や赤のLED光が気になる場合は、設定画面から「心拍数」や「血中酸素濃度」をオフにすることで、光を消すことができます。ただし、これらの機能をオフにすると、スマートウォッチの主要な健康管理機能が使えなくなる点に注意が必要です。
🔧 具体的な設定変更手順
多くのスマートウォッチで共通する設定変更方法:
- 通知設定の最適化
- 不要なアプリ通知をオフ
- 緊急連絡のみ許可
- バイブレーション強度を最小に
- センサー設定の調整
- 心拍測定:1分間隔から5分間隔に変更
- 血中酸素:自動測定から手動測定に
- ストレス測定:オフまたは1日1回に
- 通信設定の最適化
- Wi-Fi接続:自宅のみに制限
- Bluetooth:必要最小限のデバイスとのみペアリング
- データ同期:1日1回の手動同期に変更
💡 機能別電磁波削減効果
機能をオフにした場合の電磁波削減効果の推定:
- 常時心拍測定OFF:約30-40%削減
- 血中酸素測定OFF:約20-30%削減
- 通知機能最小化:約20-25%削減
- GPS機能OFF:約40-50%削減(使用時)
電磁波測定器による自宅での電磁波チェック方法
家庭で実際に電磁波を測定する方法があります。電磁界情報センターでは低周波磁界測定器の無料貸出サービスを実施しており、自宅の電磁波環境を客観的に把握することができます。
📏 電磁波測定の基本知識
電磁波測定では、以下の点を理解しておくことが重要です:
| 測定項目 | 単位 | 測定対象 | 規制値(参考) |
|---|---|---|---|
| 低周波磁界 | μT(マイクロテスラ) | 家電製品、電力設備 | 100μT(国内) |
| 高周波電界 | μW/cm² | 通信機器 | 1000μW/cm²(国内) |
| 高周波電界 | μW/cm² | スマートウォッチ | 9.5μW/cm²(スイス) |
🔍 自宅での電磁波測定手順
実際の測定で確認すべきポイント:
- 寝室の電磁波レベル
- ベッド周辺の各地点で測定
- 枕元のスマートフォン充電場所
- エアコン、照明器具からの距離
- リビングの電磁波環境
- テレビ、Wi-Fiルーターの近く
- 普段座る場所での数値
- IH調理器使用時の変化
- スマートウォッチ単体の測定
- 装着位置での測定
- 各種機能ON/OFF時の比較
- 他の電子機器との複合影響
📊 測定結果の解釈方法
測定で得られた数値の意味を正しく理解するためのガイド:
| 測定値 | 評価 | 対策の必要性 |
|---|---|---|
| 規制値の1/10以下 | 非常に安全 | 対策不要 |
| 規制値の1/2以下 | 安全範囲 | 心配なら簡単な対策 |
| 規制値に近い | 注意レベル | 対策を検討 |
| 規制値を超過 | 要対策 | 専門家に相談 |
健康管理とのバランスを考えた賢いスマートウォッチ活用法
スマートウォッチの電磁波リスクと健康管理メリットのバランスを考えた使用方法が重要です。完全に使用を避けるのではなく、メリットを最大化しつつリスクを最小化するアプローチが現実的です。
⚖️ リスクとメリットのバランス評価
| 健康管理機能 | メリット | 電磁波発生 | 推奨使用法 |
|---|---|---|---|
| 心拍数測定 | 心臓病早期発見 | 低~中 | 間隔を調整して使用 |
| 歩数計測 | 運動習慣の改善 | 最低 | 常時使用OK |
| 睡眠分析 | 睡眠の質向上 | 低 | 就寝時のみ使用 |
| ストレス測定 | メンタルヘルス管理 | 低 | 1日数回の測定 |
🏃♀️ 運動・フィットネスでの活用
運動時のスマートウォッチ使用は、健康メリットが電磁波のリスクを大きく上回ると考えられます:
- 運動強度の適正化:心拍数による運動強度管理
- カロリー消費の把握:効果的なダイエット支援
- 運動習慣の継続:数値化によるモチベーション維持
- 怪我の予防:過度な運動の抑制
💤 睡眠管理での賢い使用法
睡眠時の使用については、以下のような段階的アプローチがおすすめです:
| 使用レベル | 方法 | メリット | リスク軽減効果 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 完全に外して就寝 | 電磁波完全回避 | 最大 |
| レベル2 | 週末のみ睡眠測定 | 睡眠パターン把握 | 高 |
| レベル3 | 就寝時のみ機内モード | 測定は維持、通信停止 | 中 |
| レベル4 | 通常通り装着 | 全機能利用 | なし |
🧠 ストレス管理との組み合わせ
電磁波への不安自体がストレスになることもあります。以下のアプローチで心理的負担を軽減:
- 科学的事実の理解:正確な情報に基づく判断
- 段階的な使用:いきなり禁止せず徐々に調整
- 代替手段の確保:スマートウォッチなしでも健康管理ができる方法を併用
- 定期的な見直し:体調や生活環境の変化に応じて使用方法を調整
体に異変を感じた時の対処法と相談先
スマートウォッチを使用していて体調に異変を感じた場合の適切な対処方法と、相談すべき専門機関について説明します。症状の程度や種類によって、適切な対応が異なります。
🚨 緊急度別の症状と対処法
| 症状レベル | 具体的症状 | immediate対処 | 相談先 |
|---|---|---|---|
| 高 | 激しい頭痛、動悸、呼吸困難 | 即座に使用中止、医療機関受診 | 救急外来 |
| 中 | 持続的な頭痛、めまい、吐き気 | 使用中止、経過観察 | かかりつけ医 |
| 低 | 軽い違和感、皮膚のかゆみ | 一時使用停止、様子見 | 健康相談窓口 |
⚕️ 専門医への相談時のポイント
医療機関を受診する際に、効果的な診察を受けるための準備:
- 症状記録の作成
- 症状の発生タイミング(装着後何時間で現れるか)
- 症状の持続時間
- スマートウォッチを外した際の症状変化
- 他の電子機器使用時の症状の有無
- 使用状況の詳細
- 機種名とモデル
- 装着期間(いつから使い始めたか)
- 装着時間(1日何時間程度)
- 設定内容(どの機能を使用しているか)
- 既往歴・体質の情報
- アレルギーの有無
- 金属アレルギーの既往
- 化学物質過敏症の有無
- ストレス状況
🏥 相談可能な専門機関
症状や疑問の内容に応じた相談先:
| 相談内容 | 適切な相談先 | 特徴・専門性 |
|---|---|---|
| 急性症状 | 救急外来、内科 | 緊急性の判断と初期対応 |
| 慢性症状 | 神経内科、心療内科 | 慢性的な不定愁訴への対応 |
| 皮膚症状 | 皮膚科、アレルギー科 | 接触性皮膚炎の診断治療 |
| 電磁波不安 | 環境医学外来 | 環境要因と健康の専門的評価 |
| 妊娠中の不安 | 産婦人科 | 妊娠期の安全性評価 |
📞 その他の相談窓口
医療機関以外でも相談可能な窓口:
- 電磁界情報センター:電磁波に関する科学的情報提供
- 消費者ホットライン:製品の安全性に関する相談
- 各メーカーのサポート:製品固有の技術的問題
- 保健所:地域の健康相談窓口
まとめ:スマートウォッチ電磁波との上手な付き合い方
最後に記事のポイントをまとめます。
- スマートウォッチの電磁波測定値は2.5~7μW/cm²で、世界最厳格な規制値9.5μW/cm²を下回っている
- 実際の臨床事例では、スマートウォッチ装着で膝痛や眼瞼痙攣が悪化した69歳女性の報告がある
- WHOは30年以上の研究に基づき、スマートウォッチレベルの電磁波に健康リスクはないと結論している
- 電磁波過敏症の症状は実在するが、WHOは電磁波以外の要因(ストレス、環境、心理的要因)が原因と見解している
- スマートウォッチはBluetooth通信で2.4GHz帯の高周波を使用し、出力は携帯電話の1/25程度である
- 裏蓋の材質(金属vs樹脂)による電磁波シールド効果はほとんど確認されていない
- 妊娠中の使用について、専門機関は「胎児への影響はない」としているが、心配な場合は就寝時に外すなどの配慮は可能である
- 電磁波削減のため心拍測定や血中酸素測定の間隔延長、不要な通知機能オフなどの設定変更が有効である
- 電磁波は距離に応じて急激に減衰するため、就寝時や自宅での一時的な取り外しが効果的である
- 健康管理メリットと電磁波リスクのバランスを考慮し、完全禁止ではなく賢い使用法を選択することが重要である
- 症状を感じた場合は使用中止し、症状記録を作成して適切な医療機関に相談することが必要である
- 電磁界情報センターでは低周波磁界測定器の無料貸出サービスを提供しており、自宅の電磁波環境を客観的に測定できる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://www.hiroukaifuku.jp/y_blog/clinical-case/smartwatch_221025/
- https://denjiha.macco.co.jp/blog/smart-watch
- https://rikutaro.jp/smartwatch-unhealthy/
- https://denjiha.macco.co.jp/blog/smart-band
- https://newspicks.com/news/887916/body/
- https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/c/0000001424/?l2-id=item_SP_RelatedCategory
- https://blog.canaria-project.jp/2019/06/11/applewatch/
- https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B3%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2+%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB/568380/
- https://www.jeic-emf.jp/public/pregnancy/index/
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。