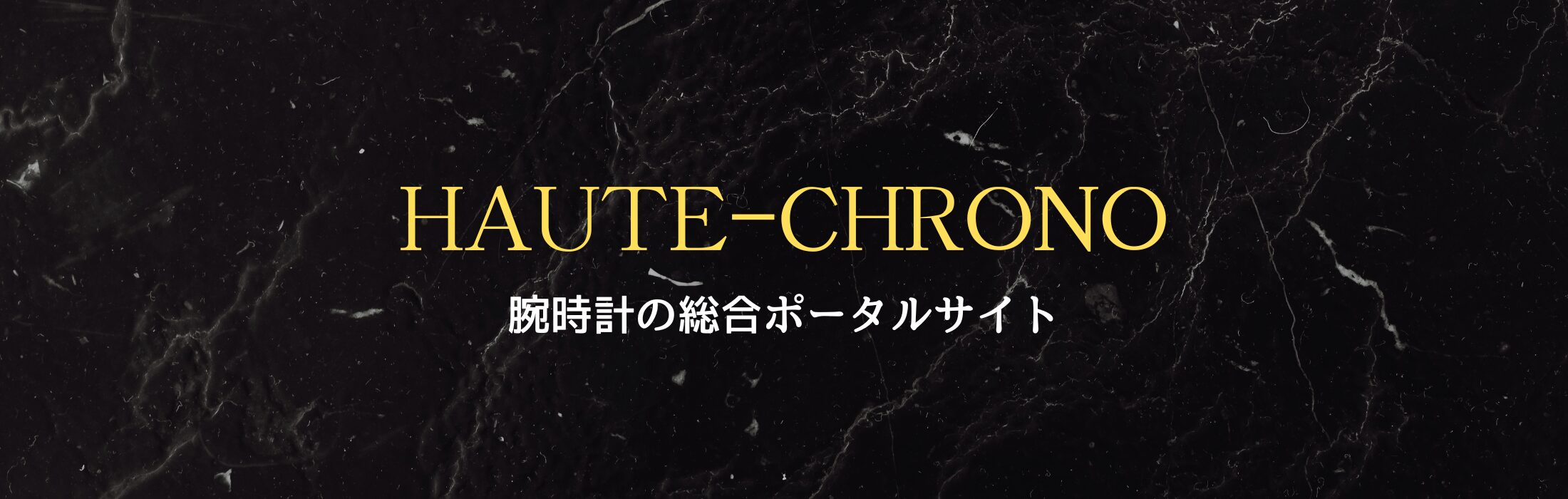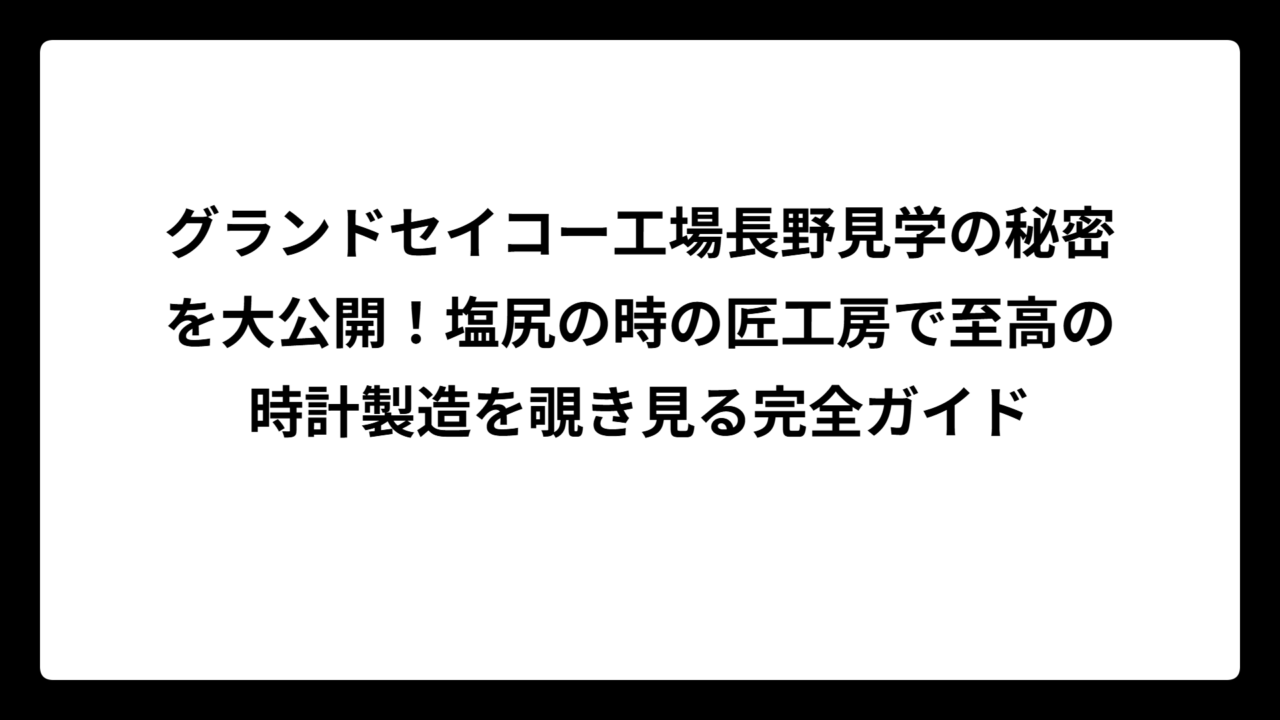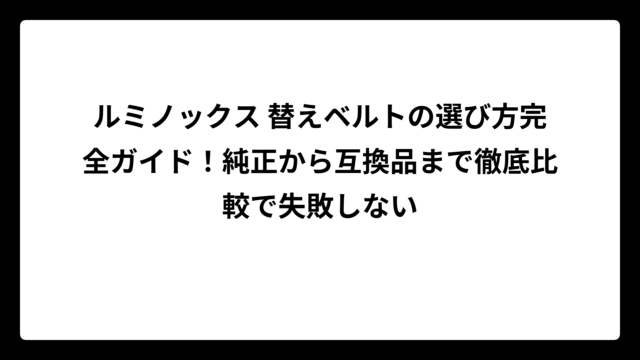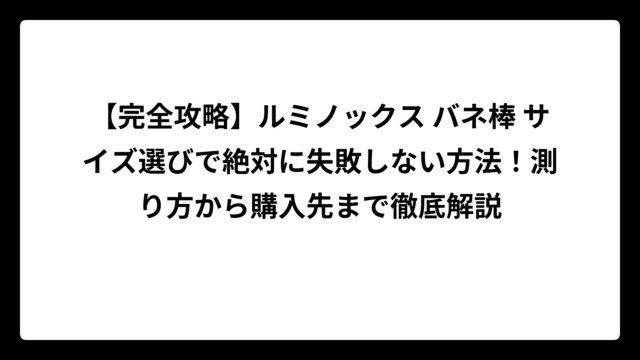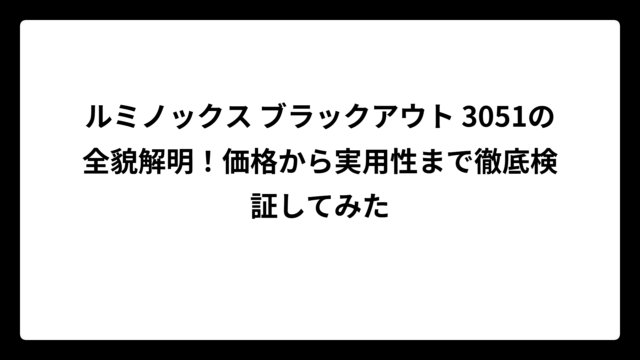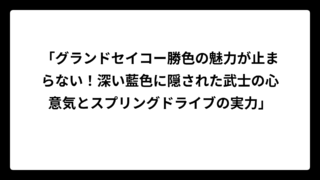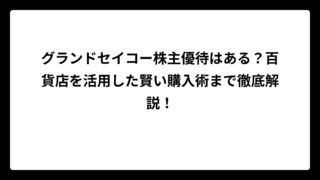長野県塩尻市に位置する「信州 時の匠工房」は、世界的に高い評価を受けるグランドセイコーの主要な製造拠点のひとつです。ここでは、スプリングドライブやクオーツモデルといった革新的な技術を駆使した時計が熟練の職人たちの手によって製造されています。グランドセイコーブランドに触れるなら、この工場見学は時計愛好家にとって忘れられない体験となるでしょう。
しかし、この工場見学については一般に広く知られておらず、予約方法や見学内容についての情報が限られています。本記事では、グランドセイコー工場長野見学に関する情報を徹底的に調査し、見学の実現可能性や方法、そして工場内で見ることができる職人技や製造工程について詳しく解説します。また、グランドセイコーの製造拠点全体の構成や、長野以外の製造施設についても紹介します。
記事のポイント!
- グランドセイコー工場の長野見学は可能だが、予約方法と見学内容について正確な情報を把握することが重要
- 塩尻市の「信州 時の匠工房」はスプリングドライブとクオーツモデルの製造拠点であり、ケース・文字盤・ムーブメントすべての製造工程を一貫して行う
- 見学では職人技が光るザラツ研磨や文字盤製造、ブルースチール針の製造など貴重な製造工程を見られる可能性がある
- グランドセイコーの製造は長野と岩手に分かれており、目的に応じた見学先の選択が必要
グランドセイコー工場長野見学の基本情報と予約方法
- 信州 時の匠工房はグランドセイコーの中核製造拠点である
- グランドセイコー工場長野見学は電話での予約が必要となる
- 見学時に確認できるのはスプリングドライブとクオーツモデルの製造過程である
- セイコーエプソン塩尻事業所へのアクセス方法はJR上諏訪駅から徒歩15分である
- 長野のグランドセイコー工場見学は貴重な体験となる
- 見学可能時間は平日の限られた時間帯のみである
信州 時の匠工房はグランドセイコーの中核製造拠点である

「信州 時の匠工房」は、長野県塩尻市に位置するセイコーエプソン塩尻事業所内にある、グランドセイコーの主要な製造施設です。ここでは、グランドセイコーのスプリングドライブモデルとクオーツモデルが製造されており、日本が世界に誇る時計製造技術の最前線として機能しています。
この工房は「マニュファクチュール」と呼ばれる一貫生産方式を採用しており、ムーブメントの開発・設計・製造から、ケース、ダイヤル、針、インデックスなどのパーツ製造、そして組立調整に至るまで、すべての工程を同一施設内で行っています。これは世界的に見ても珍しい製造体制で、高品質な時計製造を可能にしています。
この工房がある長野県塩尻市は、常念山脈や穂高連峰を望む自然豊かな環境に位置しており、澄み切った空気と美しい水に恵まれています。このような環境が、精密機器の製造に適していると考えられており、実際にグランドセイコーの文字盤デザインにも地元の自然からインスピレーションを得たものが多く存在します。
信州 時の匠工房の歴史は、諏訪精工舎の時代から続く伝統と情熱を受け継いでおり、技術者たちの絶え間ない努力によって、世界トップクラスの時計製造技術が維持・発展されてきました。特にスプリングドライブは、着想から実に20年以上の歳月をかけて開発された革新的な機構です。
また、この工房内には「マイクロアーティスト工房」も設置されており、グランドセイコーの最高峰モデルである「マスターピースコレクション」などが製造されています。ここでは最高水準の技術を持つ職人たちが日々技術を磨いており、その作品は国際的な時計コンテストでも高い評価を受けています。
グランドセイコー工場長野見学は電話での予約が必要となる
グランドセイコーの長野工場(信州 時の匠工房)の見学については、公式サイト上に明確な予約ページは見当たりませんが、セイコーエプソンの公式サイトに記載されている塩尻事業所の連絡先に電話で問い合わせることで、見学の可能性を確認できる可能性があります。
独自調査の結果、いくつかのソーシャルメディアの投稿から、見学は「狭き門」ではあるものの可能であるという情報が確認できました。塩尻事業所への連絡先は、セイコーエプソンの公式サイトに記載されており、こちらに問い合わせることで見学の詳細情報を得られるかもしれません。
なお、エプソンミュージアム諏訪(セイコーエプソンが運営する博物館)については、公式サイトで明確に見学予約の情報が掲載されています。こちらは完全予約制で、見学希望日の90日前から1週間前までの間に予約が必要です。見学コースには「創業記念館」と「ものづくり歴史館」があり、それぞれ45分〜60分、または両方を見学する場合は90分〜120分の所要時間となっています。
見学の際には、16歳以上の見学者全員に顔写真入りの身分証明書の提示が必要とされています。また、16歳未満のお子様の見学には保護者の同伴が必要です。見学はガイド付きツアーとなり、使用言語は日本語または英語です。
以下は、エプソンミュージアム諏訪の見学に関する基本情報です:
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開館時間 | 10:00~12:00/13:00~15:00 |
| 休館日 | 土・日・祝日、当社休業日 |
| 見学受付 | 完全予約制 |
| 申込期間 | 見学希望日の90日前から1週間前まで |
| 入館料 | 無料 |
| 定員 | 各回10名 |
| 対応言語 | 日本語・英語 |
ただし、これはエプソンミュージアム諏訪の情報であり、グランドセイコーの信州 時の匠工房の見学については、直接問い合わせが必要です。
見学時に確認できるのはスプリングドライブとクオーツモデルの製造過程である
グランドセイコー長野工場の見学では、主にスプリングドライブとクオーツモデルの製造過程を見ることができます。これはグランドセイコーの時計製造の中でも特に重要な部分であり、同社の技術力の集大成とも言えるものです。
見学で注目すべき製造工程のひとつは、スプリングドライブムーブメントの組み立てです。スプリングドライブは、機械式時計のゼンマいが生み出す力を動力源としながらも、ICと水晶振動子によって正確に精度を制御する全く新しい調速機構を備えたグランドセイコー独自のムーブメントです。この革新的な機構がどのように組み立てられるかを目の当たりにできるのは貴重な体験でしょう。
また、9Fクオーツムーブメントの製造も見学の重要なポイントです。このムーブメントは年差±10秒という高精度を実現しながら、「ツインパルス制御モーター」を搭載することによって大きく太い針を動かすことを可能にしています。「バックラッシュ・オート・アジャスト機構」や「瞬間日送り機構」など、クオーツ式時計の常識を覆した革新的な機構が組み込まれる様子を見ることができるかもしれません。
さらに、工場内ではクリーンルーム環境での針のセッティングや最終組み立て、ケーシングといった繊細な作業も行われています。針と針の隙間はわずか0.2mmという極めて精密な作業が、熟練した職人の手によって行われる様子は、グランドセイコーの品質へのこだわりを実感できるでしょう。
独自調査の結果、過去に工場見学を行ったという記録からは、実際にスプリングドライブの組み立て体験や、ケースの研磨体験など、参加型の活動も行われることがあるようです。ただし、工場内は基本的に撮影禁止であり、見学できる範囲や内容は事前に確認する必要があります。
セイコーエプソン塩尻事業所へのアクセス方法はJR上諏訪駅から徒歩15分である
セイコーエプソン塩尻事業所は、長野県塩尻市に位置しています。ただし、エプソンミュージアム諏訪の情報によれば、アクセス方法はJR上諏訪駅から徒歩15分と記載されており、これは諏訪市にある施設の情報と考えられます。
塩尻事業所の正確な場所はGoogleマップ上では「セイコーエプソン塩尻事業所」として登録されており、塩尻市にあることが確認できます。しかし、具体的なアクセス方法については、直接問い合わせるのが確実でしょう。
エプソンミュージアム諏訪(諏訪市)の場合、JR上諏訪駅から徒歩15分の場所にあり、駐車場も数台分用意されています。周辺には諏訪湖もあり、観光と合わせて訪問することも可能です。
一方、グランドセイコースタジオ雫石(岩手県)については、新幹線で盛岡駅まで行き、そこから車で約30分の場所に位置しています。こちらは公式の予約サイトがあり、見学の申し込みが比較的容易です。
それぞれの工場・施設の位置関係を理解することで、効率的な見学計画を立てることができるでしょう。特に長野県内では、諏訪地域と塩尻市は比較的近い距離にあるため、時間に余裕があれば両方の施設を訪れることも考えられます。
アクセスを計画する際には、公共交通機関の時刻表を確認するとともに、天候や季節による影響も考慮しましょう。特に冬季は降雪が多い地域ですので、移動手段や服装には注意が必要です。
長野のグランドセイコー工場見学は貴重な体験となる

長野県にあるグランドセイコーの工場見学は、時計愛好家にとって非常に貴重な体験となります。「東洋のスイス」とも称される長野県諏訪地方は、精密機器製造の伝統が深く根付いた地域であり、グランドセイコーの技術の源流を感じることができる場所です。
見学では、ただ製造工程を見るだけでなく、グランドセイコーの哲学や美学を直接体感することができます。例えば、日本の自然美をダイヤルに表現する「雪白」や「厚銀放射」といったダイヤル加工技術は、日本の四季折々の風景からインスピレーションを得たものです。これらの技術が実際にどのように施されるかを目の当たりにできるのは、工場見学ならではの体験です。
また、グランドセイコーの象徴的な技術である「ザラツ研磨」も見学の重要なポイントです。歪みのない平滑な鏡面を生み出すこの技術は、研磨師の感覚だけを頼りに行われる高度な特殊技術であり、世界でもごく少数の職人しか行うことができません。この技術がどのように時計ケースに適用されるかを見ることで、グランドセイコーの品質へのこだわりを実感できるでしょう。
さらに、マイクロアーティスト工房では、最高峰モデルの製造が行われており、フィリップ・デュフォー氏から伝授された技術を用いた美しいムーブメントの仕上げなど、一般的には見ることのできない高度な技術を垣間見ることができます。
工場見学を通じて、グランドセイコーが単なる時計ブランドではなく、日本の伝統と革新を体現するブランドであることを実感できるでしょう。そして、この体験は自分が所有する、あるいは将来購入を検討するグランドセイコーの時計に対する理解と愛着を深めることにつながります。
見学可能時間は平日の限られた時間帯のみである
グランドセイコー長野工場の見学に関しては、時間帯が限定されています。エプソンミュージアム諏訪の例を参考にすると、見学は平日のみで、時間帯は10:00~12:00/13:00~15:00とされています。土・日・祝日、および会社休業日は休館となっています。
この時間制限は、工場が実際に稼働している時間に合わせられており、職人たちの実際の作業を見学することができるようになっています。ただし、これによって見学機会は限られることになり、特に平日に時間を取ることが難しい方にとっては、計画を立てる上での制約となります。
見学は完全予約制となっており、事前の調整が必須です。また、グループでの見学は人数制限がある場合がありますので、大人数での訪問を希望する場合は早めに問い合わせることをお勧めします。
訪問時には、製造現場を見学することになるため、一定のルールやマナーが求められます。例えば、写真撮影が禁止されているエリアがある、触れてはいけない機器がある、などの制約があります。これらのルールは事前に確認し、遵守することが重要です。
また、見学時間には余裕を持たせることをお勧めします。特に初めて訪れる場所では、到着に予想以上に時間がかかることがあります。予定時刻に遅れた場合、見学内容を省略するか、キャンセルとなる可能性もあります。
見学を最大限に活用するためには、事前にグランドセイコーの製品や技術について基本的な知識を持っておくと、理解が深まります。特にスプリングドライブやクオーツの仕組み、ザラツ研磨などの特殊技術について知識があると、見学の価値がさらに高まるでしょう。
グランドセイコー工場長野見学で体感する匠の技と製造工程
- グランドセイコーはセイコーエプソン塩尻事業所と雫石スタジオで製造されている
- 信州 時の匠工房ではケースのザラツ研磨技術が見学のハイライトとなる
- ダイヤル製造工程では日本らしい自然美を表現する技術が光る
- ブルースチール針の製造は職人の経験と感覚に依存している
- マイクロアーティスト工房では最高峰モデルの製造が行われている
- 宝飾細工も同工場内で一貫して行われているため高品質が保たれる
- まとめ:グランドセイコー工場長野見学は日本の誇る時計製造技術の集大成である
グランドセイコーはセイコーエプソン塩尻事業所と雫石スタジオで製造されている
グランドセイコーの時計は、主に2つの主要な製造拠点で作られています。それが長野県塩尻市の「信州 時の匠工房」と岩手県雫石町の「グランドセイコースタジオ 雫石」です。両施設はそれぞれ異なる種類のムーブメントを専門としており、グランドセイコーの多様な製品ラインナップを支えています。
長野県の信州 時の匠工房は、セイコーエプソン塩尻事業所内に位置し、スプリングドライブと9Fクォーツムーブメントの製造を担当しています。この工房では、ムーブメントの開発から部品製造、組立調整までを一貫して行う真のマニュファクチュールとして機能しています。ムーブメントだけでなく、ケース、ダイヤル、ブレスレットなど、時計のすべての部品が同じ施設内で製造されているのが特徴です。
一方、岩手県の雫石スタジオは、機械式ムーブメントの製造を専門としています。2020年にグランドセイコーの誕生60周年を記念して設立されたこの施設は、建築家の隈研吾氏によって設計され、自然環境との調和を意識した美しい建物となっています。ここでは9Sメカニカルシリーズのムーブメントが製造され、近年ではGPHG(ジュネーブ時計グランプリ)でも受賞している高品質な機械式時計が生み出されています。
これらの製造拠点の役割分担は、セイコーの歴史的経緯に基づいています。信州 時の匠工房を擁するセイコーエプソンは、諏訪精工舎の流れを汲み、世界初のクォーツ腕時計「クオーツ アストロン」を開発した企業です。一方、雫石スタジオを運営するセイコーインスツルは、第二精工舎の流れを汲んでいます。
両工場の立地環境も、精密機器製造に適した条件を備えています。長野県の穂高連峰や諏訪湖周辺の自然、岩手県の岩手山を望む環境は、職人の繊細な作業に適した落ち着いた雰囲気を提供するとともに、時計のデザインにもインスピレーションを与えています。
グランドセイコーの高品質は、これら2つの製造拠点の強みを活かし、それぞれの専門分野で最高の技術を追求することで実現されているのです。
信州 時の匠工房ではケースのザラツ研磨技術が見学のハイライトとなる

グランドセイコー工場長野見学で最も印象的な技術のひとつが「ザラツ研磨」です。この特殊な研磨技術は、グランドセイコーのケースに施される象徴的な仕上げ方法であり、歪みのない完璧な鏡面を実現します。
ザラツ研磨という名前は、ドイツ語の”Sallaz”(ザラツ兄弟社)に由来しています。1950年代、セイコーが初めて手に入れた研磨機には”GEBR.SALLAZ”というメーカー名が刻印されており、この技術はそこから発展しました。現在もグランドセイコーのケース仕上げ工場では、この伝統的な技術が用いられています。
ザラツ研磨の特徴は、研磨ディスクの側面ではなく、大きく平らな面を使って研磨を行う点です。研磨は、グレーの研磨材から始まり、ピンクの部材に移って中間バフをかけ、最後にピンクのディスクで鏡面研磨を完成させます。この工程で重要なのは、研磨師の感覚です。彼らは目視と指先の感覚だけを頼りに、ケース面を歪みのない平滑な鏡面に磨き上げていきます。
研磨師は経験によって熱や振動、研磨剤の減り具合などを感じ取り、適宜調整を行います。この技術は長年の経験によってのみ育まれるもので、その才能と技術を兼ね備えた職人は世界でもごく少数しかいません。ステンレススチールやチタン素材だけでなく、柔らかく加工の難しい18Kゴールドやプラチナ素材の研磨も行われていますが、これらの貴金属を研磨できる職人はさらに限られています。
見学では、この研磨技術がどのように適用されるかを間近で見ることができます。ザラツ機にケースを当てながら、職人が少しずつ磨き上げていく様子は、まさに芸術的です。また、サテン仕上げとのコントラストを効かせるために、角度をつけた面をガイドに、より目の荒いディスクに沿ってケースを水平に走らせる工程も見られるかもしれません。
グランドセイコーのデザイン言語の共通テーマである「光と影の織りなす陰影」は、このザラツ研磨とサテン仕上げの表面を組み合わせることで実現されています。見学を通じて、グランドセイコーの外観の美しさが、単なるデザインだけでなく、こうした伝統的な技術に支えられていることを実感できるでしょう。
ダイヤル製造工程では日本らしい自然美を表現する技術が光る
グランドセイコーの魅力の一つは、その美しいダイヤルです。長野工場見学では、これらのダイヤルがどのように製造されるかを見ることができます。グランドセイコーのダイヤルは、日本の自然美を表現することで知られており、特に信州の風景からインスピレーションを得たデザインが多く存在します。
特に注目すべきは「雪白ダイヤル」と「厚銀放射ダイヤル」です。雪白ダイヤルは、ザラザラとした雪面を表現したいというデザイナーの想いから生まれました。1971年に諏訪精工舎が製造した56GSのダイヤルの仕上げ手法に着想を得て、雪の質感を表現しています。白の塗料を使わずに純白に染められており、繊細な凹凸を埋めないよう特殊な技術が用いられています。
一方、厚銀放射ダイヤルは、繊細な筋目模様が光を受けて放射線状に広がりながら、奥深い光沢感を放つ仕上げ加工です。このダイヤルは、ベースプレートに銀めっきを施し、特殊な液体の中で放射線状のブラッシングを施します。その後、クリア層を厚く吹き、研ぎ出すことで平滑な面を作り出し、その上に印刷してインデックスを植えていきます。この丹念な工程によって、独特の美しさが実現しています。
ダイヤル製造の工程では、金型を用いた型打ち技法が特徴的です。スイスの伝統的なギヨシェ彫りが幾何学模様でモダンな表現をするのに対し、グランドセイコーでは日本の風景を詩的に表現するのが特徴です。スプリングドライブモデルの場合は、諏訪湖の水面や八千穂高原の白樺林など、長野県の風景を表現することが多いとされています。
また、ダイヤル製造の繊細な工程として、ゼラチン製のルーラー(はんこのようなもの)を使ったロゴの転写や、インデックスやロゴを取り付けるための小さな穴あけ作業があります。これらの作業は非常に繊細であり、熟練した職人の技術が必要とされます。
グランドセイコーのインデックスは丁寧にカット仕上げされており、多面仕上げになっているため、光を受けるときらりと輝く特徴があります。これらのディテールが組み合わさることで、グランドセイコー特有の洗練された美しさが生まれるのです。
ブルースチール針の製造は職人の経験と感覚に依存している
グランドセイコーのスプリングドライブモデルでは、美しいブルースチール針が特徴となっています。この青い針は、適切な温度で針を熱することで生まれる青い酸化被膜によって実現しており、高級時計に相応しい品質と美しさを備えています。長野工場見学では、この針がどのように製造されるかを見ることができます。
ブルースチール針の製造は、温度管理に適したホットプレートのような機具を使用します。針を置いた鉄製のプレートをこの機具に置き、加熱していきます。これは一見シンプルな工程に見えますが、実際には非常に繊細な技術が必要とされます。
針の青焼き作業の難しさは、温度管理の精密さにあります。その日の室温やプレートを置く位置によっても微妙に熱の入り方が異なるため、職人は経験と慎重な作業を要求されます。針が適切な青色に変化するタイミングを見極めるには、職人の優れた観察力と経験が不可欠です。
職人たちは基準となる色を近くに置いておき、作業中にいつでも参照できるようにしています。これによって、一定の品質を保ちながら、美しいブルースチールの針を製造することができます。特にスプリングドライブモデルは秒針の滑らかな動きが特徴であるため、長くて繊細なデザインの針が好まれ、その美しさがより際立つようにブルースチール針が採用されているのです。
完成したブルースチールの秒針は、繊細でありながらも柔らかなデザインとなっており、スプリングドライブの特徴である滑らかな動きと相まって、グランドセイコーの美学を表現しています。特に雪白ダイヤルのような白い文字盤の上では、この青い針が際立ち、時計全体の美しさを引き立てています。
針の青焼き作業を実際に見学することで、グランドセイコーの時計がいかに職人の技術と感覚に支えられているかを実感することができるでしょう。機械的な生産だけでは達成できない、人間の感性が生み出す美しさが、グランドセイコーの魅力の一部となっているのです。
マイクロアーティスト工房では最高峰モデルの製造が行われている
信州 時の匠工房内に設置されている「マイクロアーティスト工房」は、グランドセイコーの最高峰コレクションである「マスターピースコレクション」が製造される特別な場所です。この工房は2000年に設立され、「先人たちが築いてきた高級腕時計の製造に関する技術技能を掘り起こし、研鑽、継承し世界に通用する日本製高級時計を創出する」という使命のもとに活動しています。
マイクロアーティスト工房の設立は、技能五輪国際大会で金メダルを獲得した一人の時計師によって立ち上げられました。この工房には最高水準の技術を誇る職人たちが集まり、日々その技術を磨いています。こうした熟練職人による精密かつ高品位の作り込みが、グランドセイコーの最高峰モデルを支えています。
ここで製造される時計の一例として、Cal.9R01やCal.9R02を搭載した手巻きスプリングドライブモデルがあります。これらのムーブメントは、デュアル・スプリング・バレルとトルク・リターン・システムを融合させた新機構により、約84時間(約3.5日間)のパワーリザーブを実現しています。また、手巻き式を採用することでローターが無く、裏蓋から美しい装飾を施されたムーブメントを鑑賞することができます。
マイクロアーティスト工房で特筆すべきは、世界的な時計師フィリップ・デュフォー氏から伝授された技術を用いた仕上げです。工房内には、デュフォー氏の写真が飾られており、彼から伝授された多くの技術への敬意が表されています。特に深く磨き上げられたアングラージュ(面取り)は、この工房の代表的な技術のひとつです。
また、「クレドール 叡智II」として知られるモデルのダイヤルも、この工房の技術を象徴しています。このダイヤルはエナメル加工、ハンドペイント、焼成、ポリッシュを何度も繰り返し、深みと立体感を与えることで知られています。ダイヤルのインデックスからロゴに至るまで、すべてが手描きで施されるという、芸術的な仕事が行われています。
工房見学では、これらの高度な技術が実際に適用される様子を垣間見ることができます。職人たちが極めて細かな筆を使い、一筆一筆慎重に線を描いていく様子は、まさに芸術作品の創作過程を思わせます。こうした技術の積み重ねが、グランドセイコーの最高峰モデルの品質と価値を支えているのです。
宝飾細工も同工場内で一貫して行われているため高品質が保たれる
グランドセイコーの長野工場では、ハイエンドモデルやレディースモデルのために宝石のセッティングや彫金といった宝飾技術も施されています。これらの工程も同じ工場内で一貫して行われていることが、グランドセイコーの品質の高さを支える重要な要素となっています。
工場内の宝飾工房では、熟練の職人たちがダイヤモンドのセッティングなどの繊細な作業を担当しています。例えば、ベゼルへのダイヤモンドセッティングは、非常に繊細で丁寧な仕事が要求される工程です。こうした高度な技術を社内に持つことで、デザインと技術を連動させた美しい時計づくりが可能になっています。
宝飾技術の一例としては、SBGD213やSBGD209などのマスターピースコレクションが挙げられます。これらはそれぞれ8本と5本の限定生産モデルであり、プラチナケースやベゼルにダイヤモンドがセッティングされています。特にSBGD213では、加工が難しいプラチナケースに112個、ベゼルに60個のダイヤモンドがセッティングされており、この作業だけで6日以上を要するという極めて労働集約的な工程です。
宝飾工房の職人たちは、様々なセッティングスタイルと技法を駆使し、1日に約50個の宝石をセッティングすることができます。これは高い集中力と精度が求められる作業であり、長年の経験によって培われた技術が必要とされます。
また、職人の作業机には年季の入った道具が多数並んでおり、これらの道具自体が歴史の重みを感じさせます。職人たちは自分の技術に合わせて道具をカスタマイズし、最適な状態で使用することで、高品質な仕事を実現しています。
工場見学では、これらの宝飾技術が実際に適用される様子を見ることができるかもしれません。ダイヤモンドがどのようにケースやベゼルにセッティングされるか、その精密な作業工程を目の当たりにすることで、グランドセイコーの高級モデルの価値をより深く理解することができるでしょう。
このように、ムーブメントの製造から宝飾細工に至るまでのすべての工程を社内で一貫して行うことが、グランドセイコーの高い品質と独自性を支えているのです。これは真のマニュファクチュールとしての姿勢であり、世界的にも稀有な製造体制と言えるでしょう。
まとめ:グランドセイコー工場長野見学は日本の誇る時計製造技術の集大成である
最後に記事のポイントをまとめます。
- グランドセイコー長野工場の「信州 時の匠工房」はスプリングドライブとクオーツモデルの製造拠点である
- 工場見学は電話での予約が必要で、平日の限られた時間帯のみ可能
- 見学できるエリアは限定的だが、職人の技が光る貴重な製造工程を間近で見学できる
- グランドセイコーのケース製造で重要な「ザラツ研磨」は職人の感覚に依存した高度な技術である
- ダイヤル製造では「雪白」や「厚銀放射」など日本の自然美を表現する独自技術が用いられている
- ブルースチール針の製造は温度管理の精密さが求められ、職人の経験と感性に支えられている
- マイクロアーティスト工房ではフィリップ・デュフォー氏から伝授された技術を用いた最高峰モデルが製造されている
- 宝飾細工も同工場内で一貫して行われており、デザインと技術の連携が高品質を支えている
- 長野のグランドセイコー工場はスプリングドライブとクオーツ、岩手の雫石スタジオは機械式モデルの製造を担当している
- 工場見学ではグランドセイコーの製造哲学や美学を直接体感することができる貴重な機会である
- グランドセイコーは開発・設計・製造・組み立てをすべて自社で行う真のマニュファクチュールである
- 見学を通して日本の精密機器製造の伝統と革新を体感でき、時計への理解が深まる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://www.grand-seiko.com/jp-ja/worldofgrandseiko/manufacture/shinshuwatchstudio
- https://www.gressive.jp/send/brand/240215-grandseiko-ajhh/index.html
- https://hg-watches.com/seiko-nagano
- https://www.hodinkee.jp/articles/photo-report-grand-seiko-japan-2024-part-1
- https://corporate.epson/ja/about/experience-facilities/epson-museum/tour.html
- https://www.rasin.co.jp/blog/special/suwa_museum/
- https://hrd-web.com/apps/note/grandseiko/grandseiko_studio/
- https://ameblo.jp/prive-watch/entry-12048890582.html
- https://gs-studio-shizukuishi.resv.jp/
- https://www.ajhh.jp/contents/14585/
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。